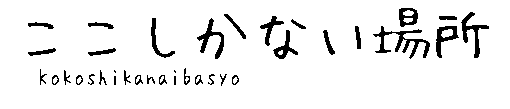さきほどからずっと、落ち着きなくダイニングを歩き回っていた富樫は、ある気配を感じて足を止める。次の瞬間、思わず周囲を見回してから、慌ててテーブルにつき、何事もないふうを装った。
軽やかな足音が廊下から響いてきて、ダイニングの前で止まる。
「――……富樫先生、終わりました」
控えめに声をかけられ、富樫はゆっくりと廊下のほうを見た。言葉を発するよりも先に、思わず顔が綻んでしまう。
広己は恥ずかしそうに視線を伏せながら、問いかけてきた。
「変じゃ、ないですか?」
「よく似合っている。デパートで羽織ったところを見たときからいいと思っていたが、きちんと着付けてもらうと、もっといいな」
本当に、先週買ってきた浴衣は広己によく似合っていた。
全体に色素が薄い広己は、その印象が際立つからといって、色合いがはっきりしたものをあまり着たがらない。そこで、富樫と一緒に選んだのが、今着ている浴衣だった。
淡い藍色に、白のストライプが入って、ところどころに紫の小さな模様が散っており、店員に選んでもらった帯とともに、広己の柔らかな雰囲気によく合っている。
やはり、浴衣を買って間違いなかった。
自分の行動の正しさに満足しながら、富樫が広己を眺めていると、廊下からひょっこりと真理子が顔を覗かせた。
伯父がいる頃から、この診療所に勤めているベテランの看護師で、仕事だけでなく、私生活でも富樫は世話になっている。例えば、広己の浴衣の着付けとか。
「満足そうね、先生。浴衣を着ている広己くん本人より、嬉しそう」
嫌なところを見られてしまったと、富樫はなんとか表情を取り繕うが、もう遅い。真理子はニヤニヤと笑っている。
「先生も変わったわねー。広己くんが来る前なら、花火大会に行くなんて、考えもしなかったでしょう? やっぱり、未来の優秀な看護師を引きとめようと、先生なりに気をつかっているのね。意外なのよ。先生がここまで面倒見がいい人だったなんて。気まじめな顔して、浴衣の着付けをしてやってくれと言い出したときは正直、この先生、どうしたのかしらと思ったわよ」
「……花火大会に行くというだけで、ここまで言われないといけないのか、俺は」
「ここまで言えるぐらい、先生の雰囲気が砕けてきたってことよ」
富樫と真理子のやり取りを聞いていた広己が、プッと噴き出してから、止められなくなったのか、口元を手で覆って笑い始める。
そんな広己の様子に目を細めてから、真理子は帰り支度をする。
「それじゃあ、帰るから。花火大会に行ったら、先生になんでも買ってもらいなさいね、広己くん」
広己は笑って頷き、真理子を玄関まで見送りに行こうとする。一方の富樫は照れ臭さもあり、座ったまま軽く片手を上げた。
「悪かったな。土曜日で午後からゆっくりしているところ、夕方からまた来てもらって」
真理子の返事は、意味深な笑い声だった。
ますます、この診療所の看護師の立場が強くなっていることを痛感してしまう。富樫が顔をしかめていると、広己がダイニングに戻ってきた。
改めて広己の浴衣姿を見た富樫は、再び顔を綻ばせて手招きした。
「……せっかくだから、写真も撮っておくか?」
富樫の目の前に立った広己は、小さく声を洩らして笑う。
「その写真を誰に見せるんですか」
「誰にも見せなくていい。俺が持っている」
イスに腰掛けたまま広己の腰に手をかけて引き寄せると、広己も素直に身を任せてくれ、肩に手を置く。
「先生も着たらいいのに。ぼくだけ着せてもらって、なんだか悪いです」
「俺が着ると、柄が悪く見える」
そんなことないですよ、と頭上から柔らかな声が降ってくる。
富樫は、浴衣に包まれたほっそりとした体を抱き締めてから顔を上げ、広己の小さな顔や髪を優しく撫でる。広己は心地よさそうに目を細めて、富樫の手の上から、自分の手を重ねてきた。
「今年はお前が忙しくて、あまり夏らしいことができなかったからな。わがままを言うなら今のうちだぞ。診療所も休みに入るし」
そうはいっても、盆休みだからと気軽に旅行などに出かけられるはずもない。なんといっても、いつ患者が来るかわからないのだ。それでも、のんびりと過ごすことはできるし、日帰り程度なら、どこかに遊びに連れて行くこともできる。
「……あの、高己がお盆に、ここに来たいって言ってるんですけど」
富樫は思わず顔をしかめる。広己の弟が遊びに来るのはかまわないのだが、違う意味で心配をしたのだ。
「それはいいが、高己くん、本当に受験は大丈夫なのか」
「本人は、余裕、と言ってました」
「速水の能天気が悪影響を与えてなきゃいいけどな……」
「大丈夫ですよ、きっと。高己はぼくより、しっかりしてますから」
見た目によらず、広己もかなりのしっかり者だと自覚はあるのだろうか――。
そんなことを考えながら富樫は、さらに広己の腰を引き寄せると、自分の膝の上に座らせる。一瞬広己は羞恥を含んだ表情を見せてから、富樫が促すまま体を預けてきた。
「夕飯は、行く途中にどこかで食べよう。……今日は車が多いぞ。駐車場から会場まで、少し歩くことになるだろうな。それに、場所取りもしてないから、立ったまま観ることになる。ああ、うちわはあったか?」
他愛ないことを話しながら、広己の背を撫でる。楽しそうに聞いていた広己が、ふいに富樫の顔を覗き込んできた。
「富樫先生もしかして、楽しみにしています?」
図星だ。広己と出会う前の富樫ならきっと、この蒸し暑い中、たかが花火を観るぐらいで出かけなくてはならないのか、と思っていたはずだ。
しかし今は、まるで子供のように気持ちが逸っている。花火がどうこうというより、その花火を楽しみにしている広己と出かけることが、富樫にとっての楽しみなのだ。
「年甲斐もなくな」
「年は関係ないですよ。――ぼくはずっと、お祭りとかに行ったことがなかったから、すごく、嬉しいです」
富樫は数秒言葉に詰まってから、両腕でしっかりと広己を抱き締める。
「……お前が行きたいというなら、どこだって連れて行ってやる。お前の控えめなわがままを叶えることが、俺は嬉しいんだからな。遠慮なくわがままになれ」
「いつか富樫先生、その言葉を後悔するかもしれませんよ。こいつがこんなに、わがままだったなんて、と」
「お前がそれぐらい、自己主張をしっかりしてくれるようになるなら、むしろ大喜びだ」
いつになく広己も気分が高揚しているのか、何も言わず富樫の首にしっかりとしがみついてきた。いや、はしゃいでいる、という表現のほうが正しいかもしれない。
首筋にかかる息遣いに刺激され、富樫は再び広己の体を優しく抱き締めたが、すぐにあることを思い出して両手を上げる。
「あんまりお前に触ったら、浴衣が着崩れするな」
「あっ」
広己も今気づいたように、慌てて立ち上がる。二人とも浴衣に慣れていないので、どれぐらいで着崩れするかわからないし、直し方などもちろん知らない。
自分の格好を見下ろしてから、広己は照れたように小さく笑う。
「どうした?」
「今の富樫先生の言い方がおかしくて……」
「普段から、お前にベタベタと触っているからな。つい癖が出た」
まじめに富樫が応じると、広己は見る間に顔を真っ赤にした。
そんな広己の様子を微笑ましく思いながら、富樫も出掛ける準備のため立ち上がる。そうはいっても、富樫の準備など、高が知れている。
服は、朝から着ているTシャツにジーンズで十分で、あとは、ちょっと鏡を覗いて髪を整えるだけだ。
ダイニングに戻ると、広己はうちわを二本用意して待っていた。
「――よし、行くか」
富樫の言葉に、広己はにっこり笑って大きく頷いた。
時間が時間だったため、花火会場からもっとも近い駐車場はどこも満車で、かろうじて、やや離れた場所に設けられた臨時駐車場に車を停めることができた。
花火を観る前に、駐車場探しで疲れ果てるところだ。
ひっそりとため息を洩らした富樫だが、車を降りた広己の嬉しそうな様子を見ると、思わず笑みがこぼれる。
花火会場に向かう人のたちの流れに加わると、富樫の隣を歩く広己の足元で下駄が鳴る。最初は歩くにくそうにしていたが、少しは慣れてきたようだ。
会場の周辺にはさまざまな露店が並んでおり、足を止めた広己は物珍しそうに眺めている。こういう反応は、子供とまるで変わらない。
無邪気というより、これまで、いろんな場所に連れて行ってもらうという経験をしていないのだろう。
微妙な距離を保ち続けている広己と、広己の実家の関係をさらにこじらせたくはないので、あえて追究するつもりはないが。
無意識に難しい顔となっていた富樫に、ふいに広己が視線を向けてくる。咄嗟に、からかうような言葉をかけていた。
「人に流されるままに、ふらふらと歩くなよ。迷子になるから」
そう声をかけた次の瞬間には、広己の顔は赤くなる。
「……そんなに危なっかしく見えましたか?」
「というより、小さな子供みたいに見えた。目がキラキラしてたぞ」
「なら、富樫先生は、そんな子供を連れた『お父さん』ですね」
予想外の返答に、富樫は言葉に詰まる。そんなに自分は老けて見えるだろうかと、本気で考え込んだぐらいだ。確かに広己との年齢差は、ギリギリで父と子と呼べるラインには入るのだが――。
「せめて、兄貴にしてくれないか」
ぼそりと富樫が言うと、きょとんとしたように目を丸くした広己が、すぐに声を洩らして笑う。
「冗談ですよ。富樫先生は、富樫先生です。ぼくにとっては、それ以外じゃありません」
「それを聞いて、安心した」
他人が聞けば耳がくすぐったくなるようなやり取りを交わしながら、露天を見て歩いているうちに、辺りはすっかり陽が落ちる。腕時計に視線を落とすと、花火の打ち上げが間近に迫っていた。
富樫は、広己にはカキ氷を、自分はペットボトルの水を買って場所を移動する。
ロープで区切られた観覧スペースだけでなく、その周辺もすでに人で埋め尽くされ、歩くのもままならない状態だった。その様子を横目に見ながら、二人は適度に空いている場所を探す。
カラン、カランとゆっくりとした歩調の広己の下駄の音が、ふいに止まる。富樫が振り返ると、広己は足元を気にしていた。
「広己?」
ハッと顔を上げた広己が、小走りで寄ってくる。
「小石が足の下に入ったみたいで」
「取れたか?」
「大丈夫です」
笑いかけてきた広己の白い顔が、鮮やかな光に彩られる。重々しい音も響き、体が震えた。空を見上げると、花火が続けざまに打ち上げられているところだ。寸前にアナウンスが流れていたが、どうやら花火大会の開始を告げる内容だったらしい。
「……始まったな」
そう呟いた富樫は、広己の手首を掴んで周囲を見回し、ちょうど人垣の間のわずかなスペースを見つけ、なんとか観覧場所を確保した。
序盤なのでまだ大きな花火は上がらないが、それでも空に広がる華やかな色と大きな音の迫力は見事なものだ。
一回目の花火が打ち上がったあと、少し間が空く。広己は、自分がカキ氷を持ったままなのを思い出したのか、慌てたように口に運ぶ。
今夜はやけに子供っぽく見えるなと思いながら、富樫は優しい眼差しで広己の横顔を見つめる。こういうときの自分は確かに、広己の恋人というより、保護者――父親のような気持ちでいるのかもしれない。
「美味いか?」
カキ氷の味など、どこで食べようが大差ないのだろうが、つい尋ねてしまう。すると広己が、カキ氷のカップを差し出してくる。
「食べますか?」
蒸し暑い中、水を飲むだけでは物足りないものを感じ、富樫は遠慮なく分けてもらうことにする。代わりに広己には、ペットボトルを渡した。
カキ氷を一口食べると、冷たい感触が舌の上で溶け、二口、三口と食べているうちに、ほんのわずかな間だけ、汗が引く。隣では広己が、ペットボトルに口をつけていた。
「……来年は張り切って、場所取りするか。やっぱり座ってゆっくり観たいよな」
「そのときは、みんな一緒がいいですね。ぼくと富樫先生だけなら――どこで観てもいいんです」
はにかんだような表情を向けられ、富樫は広己が言おうとしていることを理解する。同時に胸の奥がじんわりと温かくなった。
広己は、出会ったばかりの頃に比べれば、ずいぶん感情を素直に口にするようになった。それは自分のおかげだと言う気はない。広己なりにいろんな経験をして、いろんなことを考えている日々の積み重ねのおかげだ。
その変化をまっさきに感じ取れる位置に自分がいることに、富樫は感謝している。そして、幸せだった。
次の花火が上がり、二人は自然に視線を空へと向ける。
いよいよ大きな花火が続けて打ち上げられるようになると、観客はさらに多くなり、富樫たちの背後にも人が押し寄せてくる。
「あっ」
人の勢いに押された広己が小さく声を洩らしてよろめき、富樫はすかさず腕を掴んで引き寄せ、自分の前へと立たせる。これで、背後からいくら押されようと、ある程度は守ってやれる。
富樫は何も言わず広己の手からペットボトルを取り上げ、代わりにカキ氷のカップを持たせた。
花火の合間にカキ氷を食べているのか、空を見上げていたかと思えば、次の瞬間には顔を伏せる広己の姿を見下ろしながら、富樫はつい笑ってしまう。本当に、子供を連れている気分だった。
周囲の人の密度が増し、必然的に富樫は広己に体を寄せることになる。広己の背に胸元が触れると、わずかだが、広己のほうから体を寄せてきた。
富樫が笑みをこぼした瞬間、頭上からまばゆい光が降り注ぎ、周囲から歓声が沸く。これまでで一番大きく、色鮮やかな花火が上がったのだ。
誰もが花火に意識を奪われている中、富樫は広己の片手を探り当て、握り締める。すると広己のほうも、キュッと握り返してきた。
最後までじっくりと花火を観ていたかったが、帰りの混雑を思い、終了予定時間の少し前に広己に声をかけて会場を離れる。
露天が並ぶ通りは、富樫と同じことを考えたのか帰る人たちで溢れていたので、別の道を通る。
背後から広己の下駄の音がついてきているが、ときおりその音が乱れ、止まる。そうかと思えば、慌てた様子で追いかけてくる。自分の歩調が速いのだろうかと心配になり、富樫は足を止めて振り返る。
ようやく気づいたが、広己は足を引きずっていた。何が原因か、すぐに察しがつく。
「鼻緒で擦れて痛いのか?」
「……少し」
富樫は広己の足元に屈み込み、どうなっているか見ようとしたが、離れた場所にある街灯の明かりがここまで届かず、暗くてよく見えない。
「いまさら言っても遅いが、鼻緒の部分だけでも揉んで、柔らかくしておけばよかったな」
立ち上がった富樫は、真剣な顔で広己に問いかけた。
「なんなら、車まで背負ってやろうか?」
一拍置いてから、広己が勢いよく首を横に振る。
「そんなことっ……。大丈夫です。歩けますから」
きっと今、広己は顔を真っ赤にしているのだろうなと思うが、残念なことに、顔色の変化も見ることができない。
広己に合わせてゆっくりとした歩調で歩きながら、花火の余韻に浸る。
「お前のおかげで、久しぶりに花火が観られた」
「ぼくは、富樫先生のおかげで観られたと思っていますよ」
「……ならまあ、お前の発案と、俺の行動力のおかげ、ということにしておくか」
クスクスと笑ってから、はい、と広己が答える。
なんとか車に戻ると一息つく間もなく、駐車場を出るところから早速、渋滞に巻き込まれる。これも織り込み済みの事態なので、いまさら苛立ったりはしない。
助手席で広己は下駄を脱ぎ、人心地ついたように吐息を洩らす。
「疲れたか?」
スピードを抑えて車を走らせながら問いかけると、駐車場横の自販機で買ったお茶を飲んでいた広己が首を横に振る。
「少しも。むしろ、富樫先生のほうが大丈夫ですか? 午前中は診療で、今はこうして車を運転して」
「たまには、こういうことで体を使うのもいい。お前がいなかったら、外に出て気分転換することもないんだしな」
何より、広己の楽しそうな様子を見られたのだから、満足している。それに花火もきれいだった。
おそらく広己のことなので、高己に報告して、その高己が速水に報告するだろう。そして速水は、どうして誘ってくれなかったのかと、富樫に電話をかけてくるのだ。
もっとも広己は、そんな富樫と速水のやり取りを、にこにこしながら眺めているのだろう。
やはり痛むのか、広己が前屈みとなって自分の足元を見ている。富樫が横目でちらりとうかがうと、少し乱れた浴衣の襟元から、華奢さを感じさせる鎖骨のラインが覗き見えた。
普段ならなんでもないはずなのに、この瞬間、富樫はひどくうろたえてしまい、慌てて正面を見据える。
「……帰ったら診てやろう」
「絆創膏を貼っておけば平気だと思いますよ」
「診たいんだ」
大人げなく、ややムキになって言うと、広己が笑い声を洩らす。いつになく、今日の広己はよく笑う。
少し車を走らせると、すぐに停まる渋滞の列に嫌気が差し、富樫はハンドルから手を離す。隣では広己が、ウインドーに張り付くようにして傍らの海を眺めていた。家のすぐ側も海なのだから、いまさら珍しいこともないだろうと思うのだが、子供のような広己の姿がなんだか微笑ましい。
富樫はそっと片手を伸ばし、広己の後ろ髪をさらりと撫でた。驚いたように振り返った広己の頬にも触れると、目を細めた広己のほうから頬を寄せてくる。
この瞬間、むしょうに広己を抱き締めたい衝動に駆られたが、前後を車に挟まれた状態では、そんな大胆なことはできない。富樫は別に気にしないが、神経が細やかな広己はそうもいかない。
前の車が少しずつ進み始めたのを機に、触れていた広己の頬から手を離す。
運転に集中しながらも、富樫は前を見据えたまま、気が急いているのを感じていた。早く広己と二人きりになりたかったのだ。
歩いたほうが早いだろうと思わせる渋滞をようやく抜け、やっと自宅に帰り着いたとき、ちょうど電話が鳴っていた。
広己に戸締りをしっかりするよう言い置いて、靴を脱ぎ捨てた富樫はダイニングに駆け込み、子機を取り上げる。
この時間、自宅にかかってくる電話は、急患以外だとごく限られている。
速水だったら叩き切ってやろうと思いながら電話に出たが、相手は、ある意味予想外といえる人物だった。
「高己くん?」
広己の弟からの電話に、富樫はわずかに戸惑う。
富樫の、高己に対する感情は非常に複雑だった。高己から、兄である広己を取り上げてしまったという負い目にも似たものを感じているからだ。高己本人がいい子であるだけに、なおさらその気持ちが強い。
『あっ、富樫先生? こんばんは』
「あ、あ……」
高己はいつも、屈託がない。広己と暮らして物静かな雰囲気に馴染んでいると、ときどき顔を合わせる高己の明るさに面食らうときがある。それは話していても同じだ。
「広己ならすぐに――」
『違います。兄貴じゃなくて、富樫先生に話があったんです。兄貴から、お盆にそっちに遊びに行くという話は聞きましたか?』
「ああ、それなら聞いた。速水同伴じゃなく、君一人なら歓迎だ」
あはは、と声を上げて高己は笑う。
『俺一人です。それで、よろしくお願いしますと、富樫先生に言っておこうと思って』
どこかの悪友と違って律儀だなと思いながら、富樫は笑みを浮かべる。ちょうどそこに広己もやってきたが、下駄から解放されて楽になったのか、足を引きずっていない。
「いつでも来るといい。君がいると、広己も喜ぶ。……唯一心配なのは、君が受験生ということぐらいだな」
富樫の言葉で電話の相手がわかったらしく、広己が目を丸くする。
『勉強道具は持っていきますから、ご心配なく。わからないところがあれば、兄貴がいるし。兄貴、ぼんやりしているように見えて、頭いいんですよ』
「よく知っている」
広己が側に寄ってきたので、肩を抱き寄せる。一方で電話の向こうの高己にはこう言った。
「広己に代わろうか? すぐ側にいる」
『いいです。どうせ明後日には会えるし』
あっさりと電話は切られ、いくぶん拍子抜けしながら富樫は子機を置いた。
「高己ですか?」
「ああ。お盆に行くから、よろしくお願いします、だそうだ。速水や千沙子より、よっぽど礼儀正しい」
「富樫先生が怖いんじゃないですか」
さりげなく重大なことを言われ、一瞬動きを止めた富樫は、すぐに広己の顔を覗き込み、真剣な顔で問いかけた。
「……そんなに俺は怖いか?」
広己は笑みをこぼして富樫の肩に額を押し当ててくる。
「怖くないですよ、ぼくは。でも高己は、よく富樫先生と速水先生がふざけ合ってケンカしているところを見ているから、少し誤解しているかもしれません」
別にふざけて速水とケンカしているわけではないのだが――。本気でケンカしていると言うのも語弊がある気がして、あえて訂正しないでおく。
富樫は広己の頭を抱き締めながら髪に唇を押し当て、優しい声で囁いた。
「お盆は、兄弟でのんびりすればいい。俺は邪魔だろうがな」
「そんなことないですよ」
ここでようやく、広己の足のことを思い出した富樫は、体を離して屈み込む。明るいところで広己の両足を見ると、鼻緒が当たっていた指の間から血が滲んでいた。靴擦れがひどくなったような感じだ。
「痛かっただろう……。待っていろ。すぐに手当てしてやるから」
「本当に絆創膏を貼るだけで――」
広己の肩を押してイスに座らせ、富樫は持ってきた救急箱を開ける。再び広己の足元に屈むと、少し沁みることを告げて、傷を消毒する。それから丁寧に軟膏をすり込み、小さく切ったガーゼを当ててテープで留める。
「もう少し傷口が渇いたら、希望通り絆創膏を貼ってやる」
「……ありがとうございます」
立ち上がろうとした富樫だが、気が変わる。床に座り込むと、広己の両足を抱えるようにして抱き締めた。
「富樫先生……」
ぽつりと洩らした広己の手が頭にかかり、髪を撫でられる。これでは、いつもと立場が逆だが、たまには悪くなかった。富樫が広己に甘えるという行為も。
「もう少しの間、浴衣を着ていてくれるか?」
頭上から降ってきたのは、柔らかな声だった。
「富樫先生は気づいてないでしょう? ぼくは、富樫先生にもっとわがままになってもらいたいと思ってるんです。富樫先生の唯一の欠点ですね。ぼくにわがままを言わないのは」
一本取られた――。
富樫は声を洩らして笑いながら、浴衣に包まれた広己の膝に額を押し当てた。
Copyright(C) 2007 Nagisa Kanoe All rights reserved.
無断転載・盗用・引用・配布を固くお断りします。